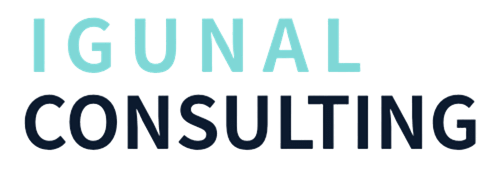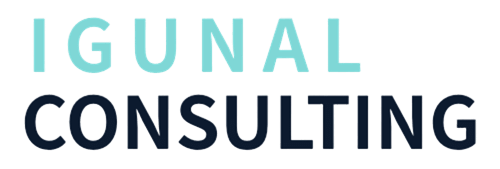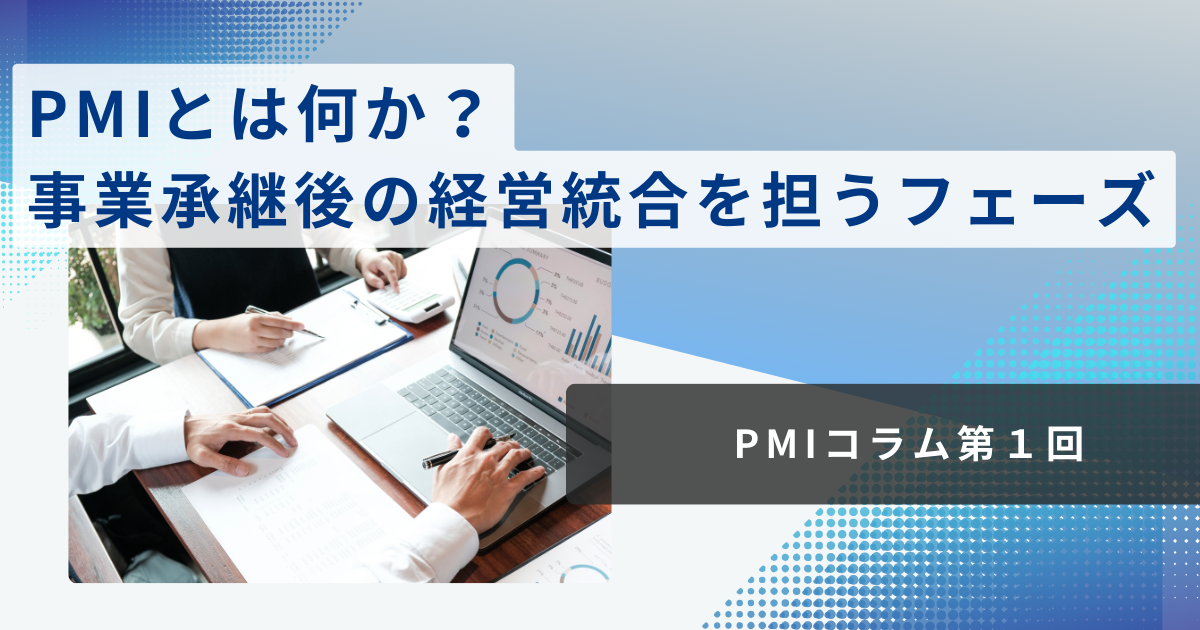「M&Aが成立した。これでひと安心」――そう感じた経営者は少なくありません。
しかし、譲渡契約が締結された日は、「終わりの日」ではなく「始まりの日」です。
M&A後の経営をどう立て直すか。
従業員や取引先との関係をどう築くか。業務のやり方をどう整えるか。
このような「統合の作業」を、PMI(Post Merger Integration)と呼びます。
PMIへの取り組み方によって、事業承継が「会社を次世代に残すことができた成功」になるか、「混乱を招いただけの失敗」になるかが、大きく変わります。
本記事はPMIシリーズの第1回です。
「PMIとは何か」「なぜ今、中小企業にも重要なのか」「何をするものなのか」を、できるだけわかりやすくお伝えします。
- PMI(Post Merger Integration)とは、事業承継・M&A後の「経営統合プロセス」全体を指す言葉です
- 「M&Aの成約=ゴール」という誤解が、承継後の混乱を招く最大の原因のひとつです
- PMIの本質は「数字を合わせること」ではなく、「人と組織をつなぎ直すこと」にあります
- 中小企業庁「中小PMIガイドライン」により、中小企業でも実践できる標準的な手順が整備されました
- PMIは「特別な専門知識が必要な難しいもの」ではなく、事業承継に取り組むすべての経営者に関係します
PMIとは何か――「統合」こそがM&Aの本番
PMIの正式な意味
PMI(Post Merger Integration)とは、M&Aや事業承継が成立した後に行う、経営・組織・業務・人材などを統合するための一連の取り組みのことです。
日本語に訳すと「合併・買収後の統合」となります。
中小企業庁の「中小PMIガイドライン」では、PMIを次のように位置づけています。
「M&Aの目的を実現させ、統合の効果を最大化するために必要なプロセス」
要するに、「M&Aで何を達成したかったのか」という目的を、実際に形にするための作業がPMIです。
PMIが扱う範囲は幅広い
PMIが対象とするのは、財務や法務だけではありません。
具体的には次のような領域が含まれます。
経営統合
新しい経営方針の策定・共有、意思決定ルールの整備、KPI(目標指標)の設定など、経営の「軸」をつくる作業です。
PMIの中でも最も優先度が高く、承継後できるだけ早く着手すべき部分です。
信頼関係構築
従業員・取引先・金融機関などとの信頼関係を新たに築く取り組みです。
M&A直後は関係者の不安が高まっているため、丁寧なコミュニケーションが欠かせません。
業務統合
業務プロセス・ITシステム・会計管理・人事制度などを整備・統合する作業です。
短期間で完了するものと、1年以上かけて進めるものが混在します。
PMIの本質は「人と組織をつなぎ直すこと」
PMIを「財務的な作業」や「手続きのこと」と捉える方は少なくありません。
しかし実際のPMIで最も難しく、かつ重要なのは「人」にまつわる課題です。
- 従業員が「自分の仕事や処遇はどうなるのか」と不安を抱えていないか
- 前の経営者への信頼が厚く、新しい経営者をなかなか受け入れられない雰囲気はないか
- 組織の暗黙のルールや価値観が、新経営者の考え方とぶつかっていないか
これらを放置したまま数字だけを統合しようとしても、組織は動きません。
PMIの本質は、「事業の数字を合わせること」ではなく、「人と組織をつなぎ直し、新しい経営を受け入れてもらうこと」にあります。
なぜ今、PMIが注目されているのか
中小企業のM&A件数が急増している
日本では経営者の高齢化が急速に進んでおり、後継者不在のまま廃業を迎える中小企業が増えています。
状況を背景に、親族外承継やM&Aによる事業引継ぎの件数は年々増加しています。
M&Aは、後継者問題を解決する有効な手段のひとつです。
ただし、M&Aが成立しただけでは、事業が安定・成長するわけではありません。
その後の経営統合(PMI)がうまくいって初めて、M&Aは意味を持ちます。
「M&Aの成約=ゴール」という誤解が失敗を招く
中小企業庁の調査によれば、M&Aを実施した企業のうち約24%が、承継後の満足度が期待を下回ったと回答しています。
満足度が低かった主な理由として挙げられるのが、「PMIへの取り組みが不十分だった」ことです。
契約成立に向けて多大なエネルギーを注いだ結果、「契約が済んだら一段落」という意識になりやすく、その後の統合作業がおろそかになるケースが少なくありません。
PMIを軽視すると、次のような問題が起きやすくなります。
- 従業員の不安や不満が高まり、離職につながる
- 取引先からの信頼が失われ、売上が落ちる
- 経営方針が伝わらず、現場が混乱したまま動けなくなる
- 前の経営者への依存が解消されず、事業運営が止まる
中小PMIガイドラインで「型」が整備された
以前は、PMIの取り組み方は「担当者の経験や勘」に頼ることが多く、体系的な手順が確立されていませんでした。
この状況を受け、中小企業庁は2022年3月に「中小PMIガイドライン」を公表しました。
このガイドラインは、中小企業でも実践できるPMIの「型」を示したもので、以下の内容が整理されています。
- PMIで取り組むべき3つの領域(経営統合・信頼関係構築・業務統合)
- フェーズごとの進め方(プレPMI → 100日プラン → 中期 → 定着)
- 成功事例・失敗事例をもとにした具体的なポイント
- PMI分析ワークシート・アクションプランなどの実践ツール
ガイドラインの公表により、PMIは「一部の専門家だけが扱う特別な作業」ではなく、事業承継に取り組むすべての中小企業に関係する身近な取り組みとして認識されるようになりました。
PMIは「昔から行われていた作業」に名前がついたもの
「PMI」という言葉は最近普及しましたが、PMIの本質的な作業自体は、以前から現場で行われてきたものです。
たとえば、後継者が事業を引き継いだとき、次のようなことは当然のように行ってきたはずです。
- 従業員一人ひとりと話し合い、「これからどうしていくか」を伝える
- 取引先へのあいさつ回りを行い、今後の関係継続を確認する
- 前の経営者がひとりで把握していた業務の流れや顧客情報を引き継ぐ
- 経理や給与計算のやり方を把握し、必要に応じて整理する
これらはすべて、PMIの一部です。
「PMIとは何か難しいもの」ではなく、「事業承継後にやるべきことを体系的に整理したもの」と理解していただけると、ぐっと取り組みやすくなります。
PMIに取り組まないと何が起きるか
PMIを意識せずに承継後を過ごすと、どのような問題が起きやすいのでしょうか。
典型的なパターンを整理します。
従業員の不安が解消されない
「自分の仕事はなくなるのか」「給料は変わるのか」「新しい社長はどんな人なのか」。
M&A後の従業員は様々な不安を抱えています。
これを放置すると、モチベーション低下や離職につながります。
前の経営者への依存が解消されない
中小企業では、営業・技術・人間関係など、多くのことが前経営者個人の「頭の中」にあることが少なくありません。
引き継ぎが不十分なまま承継が完了すると、日常業務に支障が生じます。
取引先との関係が不安定になる
長年の人間関係で成り立っている取引が多い中小企業では、「社長が変わった」という事実だけで取引先の不安が高まることがあります。
早めの報告・あいさつが欠かせません。
「なんとなく経営」が続いてしまう
承継後も経営方針が明確にならないまま日常業務をこなすだけでは、M&Aの目的(事業成長・効率化など)は達成されません。
PMIと事業承継の関係――「承継+統合」でひとつの取り組み
事業承継とPMIは、切り離せない関係にあります。
事業承継とは、「会社・事業を次の世代に引き継ぐこと」です。
一方、PMIとは「引き継いだ後に、経営を安定・成長させるための統合作業」です。
事業承継で「誰に渡すか」「どうやって渡すか」を決め、PMIで「渡した後をどう育てるか」を実行する。この両輪が揃って初めて、承継は「成功した承継」といえます。
中小PMIガイドラインでも、PMIはM&A成立前の準備段階(プレPMI)から、成立後数年にわたるプロセス(ポストPMI)まで含めた、長期にわたる取り組みとして定義されています。
よくある質問(FAQ)
- QPMIはM&Aのときだけ必要なのですか?
- A
いいえ、親族承継や従業員承継でも必要です。「身内に渡した」「信頼できる従業員に任せた」という場合でも、経営方針の引き継ぎ・信頼関係の再構築・業務の整備は必要です。形式的な承継が済んでも、PMIなしでは経営の実質的な引き継ぎは完成しません。
- QPMIには専門家が必要ですか?
- A
必ずしも専門家が必須というわけではありませんが、初めて承継に取り組む場合は中小企業診断士などの専門家に相談しながら進めることをお勧めします。中小PMIガイドラインも「M&AやPMIに関する知見・経験が乏しい場合は、専門家に相談しながら取り組むことが望ましい」と明記しています。
- QPMIはいつから始めればよいですか?
- A
中小PMIガイドラインでは、M&A成立前の段階(プレPMI)から準備を始めることを推奨しています。少なくとも、M&A成立と同時に取り組みをスタートすることが大切です。「成立してから考えよう」では遅れをとりやすくなります。
- QPMIにどのくらいの期間がかかりますか?
- A
PMIは一度で完了するものではなく、数年単位で継続するプロセスです。特に最初の100日間(100日プラン)が最重要期間とされており、この間に経営方針の共有・信頼関係の構築・現状把握を集中的に行います。その後も、中期的な業務統合・制度整備を経て、徐々に組織が定着していきます。
まとめ
PMI(Post Merger Integration)とは、事業承継・M&A後に経営・組織・業務を統合していく一連のプロセスです。
- M&Aの成約はスタートであり、ゴールではありません
- PMIの本質は「財務の統合」ではなく「人と組織をつなぎ直すこと」にあります
- 中小企業庁「中小PMIガイドライン」により、中小企業でも実践できる「型」が整備されています
- PMIは特別難しいものではなく、事業承継後に「やるべきこと」を体系化したものです
次回(第2回)では、「なぜ中小企業においてPMIがとくに重要なのか」を、具体的な背景や統計データを交えて解説します。
PMIシリーズの記事一覧
| 回 | タイトル | 内容 |
|---|---|---|
| 第1回 | PMIとは何か(本記事) | PMIの定義・なぜ必要か |
| 第2回 | なぜ中小企業においてPMIが重要なのか? | 中小企業特有の課題とPMIの必要性 |
| 第3回 | PMIが失敗する典型的なパターンと回避策 | 失敗事例と対策 |
| 第5回 | PMI成功のカギ――リーダーシップとコミュニケーションの力 | 経営者に求められる姿勢 |
| 第6回 | PMI実施手順――100日プランと成功のポイント | 具体的な実施ステップ |
| 第7回 | PMIにおける人材マネジメントと組織文化の融合 | 人材・文化の統合 |
| 第8回 | PMIにおける財務・業務プロセス統合――資金繰りとシステムの整備 | 財務・業務の実務的統合 |
| 第9回 | PMIの成果を測る――KPI設定とモニタリングの方法 | 成果の見える化と管理 |
| 第10回 | PMIの総括と今後の展望――中小企業における可能性と支援制度の活用 | シリーズのまとめと支援制度 |
事業承継・PMIでお困りの方へ
イグナル・コンサルティングでは、M&A・事業承継後のPMI支援を行っています。
当事務所の支援スタンスは、「事業のなりたい姿の実現を最優先に」することです。
PMIの取り組みも、補助金の活用(事業承継・M&A補助金など)も、すべて「事業がどうなりたいか」という目的から設計します。
「何から手をつけてよいかわからない」という段階からのご相談も歓迎しています。
参考資料
- 中小企業庁「中小PMIガイドライン」(令和4年3月)
- 中小企業庁「中小PMIハンドブック」
- 中小企業庁「PMI実践ツール活用ガイドブック」(令和6年3月)